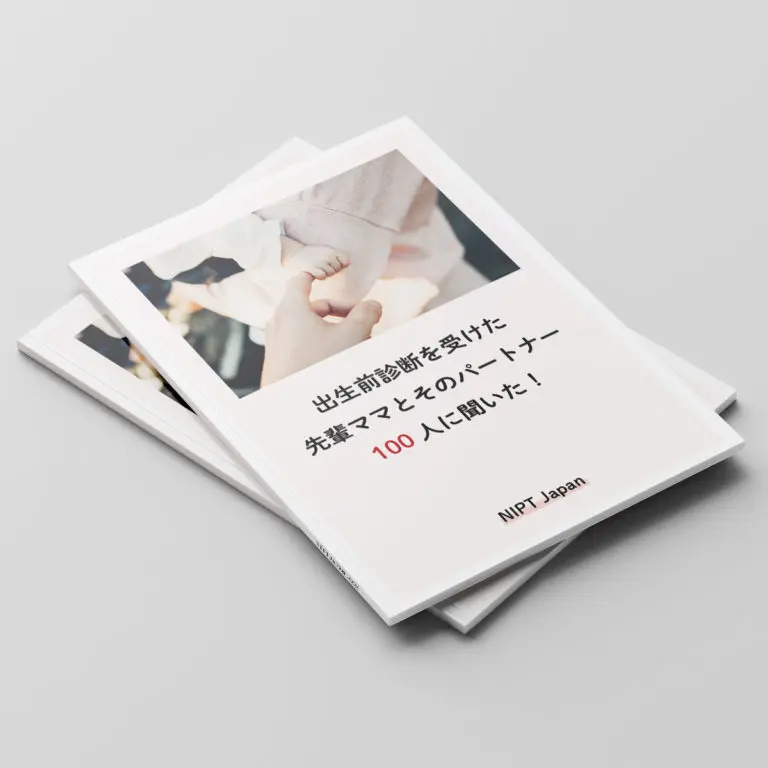つわりがおさまり、お腹の赤ちゃんもどんどんと大きくなる妊娠安定期。
妊婦さんにとっても、安定期に入ると安心できて、うれしい時期だと思います。
この妊娠安定期とはいつ頃からなのか気になりますよね。
妊娠安定期前後に気を付けなければならないことも含め、妊娠安定期における注意点や過ごし方について、詳しく解説していきます。
妊娠安定期はいつから?

妊娠安定期とは、定義はありませんが一般的に妊娠16週目(妊娠5か月)から妊娠27週目(妊娠7か月)の頃のことをいいます。
この頃になると、胎盤が完成し、流産のリスクが低下するとともに、つわりも軽減するため、母子ともに安定した状態となります。
妊娠5か月頃の子宮の大きさは大人の頭の大きさくらいです。
妊娠5か月から、子宮のてっぺんから恥骨の上までの長さである子宮底長の測定が可能となります。
お腹のふくらみも少しずつ目立つようになる時期ですが、妊娠16週では洋服を着ていると妊婦さんであることはわからないかもしれません。
つわりの症状は落ち着く人が多いですが、個人差があります。
妊婦さんの中には、安定期に入ってつわりがおさまったと思ったら、ぶり返してしまった人もいます。
早い人では妊娠16週くらいから胎動を感じますが、初産の場合は妊娠20週くらいに胎動を感じる人が多いようです。
胎動を感じると赤ちゃんがお腹にいると実感でき、喜びもひとしおでしょう。
胎動を感じたら、お腹を優しくマッサージしたり、話しかけたりして赤ちゃんとのコミュニケーションを図りましょう。
妊娠安定期には、個人差はありますが、お腹の張りを感じやすくなります。
これは、妊娠中期(妊娠5~7か月)になると急に子宮が大きくなるためですが、痛みがなければ心配ありません。
痛みや性器からの出血を伴うお腹の張りの場合は、すぐに病院を受診しましょう。
妊娠安定期前は何に気をつければよいのか?

妊娠安定期前にはどのようなことに気をつければいいのでしょうか。
3つの注意点について見ていきましょう。
安易に薬を飲まない
妊娠中の薬の服用については、心配な妊婦さんも多いでしょう。
妊娠中の薬の服用については、慎重になるべきですが、多くの薬は妊娠中に服用しても赤ちゃんに問題はありません。
まずは、正しい知識を持つことが大切です。
薬は自己判断で安易に服用せず、主治医とよく相談の上、服用しましょう。
飲酒をしない
妊婦さんが飲酒をすると、生まれてくる赤ちゃんにさまざまな影響が出る可能性があります。
これを胎児性アルコール症候群と言います。
出生時の低体重などに加えて、最近ではADHDなど広範囲で影響を及ぼすことがわかっています。
この胎児性アルコール症候群には、治療法はありません。
唯一の対処法として、妊娠中には完全に断酒することが大切です。
タバコを吸わない
妊娠中の喫煙は、早期破水や早産、胎盤異常などの原因となります。
胎児の成長が制限される危険性もあり、低出生体重の可能性も高まります。
このほかにも、妊娠中の喫煙と関連することとして、子宮外妊娠や自然流産の可能性が指摘されています。
このようなことから、妊娠中の喫煙はもちろんNGで、受動喫煙にも気をつけましょう。
妊娠安定期の過ごし方

つわりが治まり、できることが増える妊娠安定期。
妊娠安定期には、出産に向けての準備をしながら、この時期にしかできない体験をすることが大切です。
具体的な過ごし方としては、下記のようなものが挙げられます。
- こまめに有酸素運動を行う
- 両親学級への参加
- 注意点を守った性生活
- マタニティフォトを撮る
では、それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
こまめに有酸素運動を行う

妊娠の経過に問題がない場合、適度な運動をするとよいでしょう。
手軽にできるウォーキングやマタニティヨガ、マタニティスイミングなどの有酸素運動がおすすめです。
こまめに有酸素運動を行うことで、運動不足が解消でき、気分転換にもなります。
市区町村の保健所や妊娠健診を行っている施設でマタニティヨガなどが実施されていることもあります。
必ずしも教室などに通う必要はありませんが、興味がある方は内容やスケジュールを確認してみましょう。
このような教室に通うことは、同じ時期に赤ちゃんを出産する友達を作るきっかけにもなります。
ただし、切迫早産の兆候がある場合や胎盤の位置異常などにより、運動を控えなければいけない人もいます。
運動をする際は、医師に相談し、指示に従いましょう。
体調が悪い時には無理をせずに休み、もし運動の最中にお腹が張るようなことがあれば、すぐに中断してください。
運動においては、なによりも楽しく、リフレッシュすることが大切です。
両親学級への参加

妊娠安定期での出産準備の一つとして、両親学級への参加が挙げられます。
両親学級では、妊娠中の過ごし方や出産がどのように進むのか、そして産後の赤ちゃんのお世話の方法などを学ぶことができます。
立ち会い出産を希望する場合などに、産院主催の両親学級への参加が求められる場合もあります。
両親学級では、パートナーが妊娠後期のお腹と同じ重さの「妊娠ジャケット」を着て、妊婦さんの身体の変化を体感する機会を設けることもあります。
これは、妊婦さんへの理解をさらに深められる体験となるでしょう。
また、妊娠・出産のプロである産婦人科医や助産師などから直接指導を受けることができるため、正しい知識の習得ができます。
妊婦さんとパートナーの2人で参加することにより、一層絆も深まります。
パートナーにとっては、赤ちゃんを迎える自覚が芽生える貴重な機会となるはずです。
注意点を守った性生活
妊婦さんの体調が良好であれば、セックスをすることは問題ありません。
ただし、妊娠中期の半ばとなると、お腹が出てくるため、セックスをしにくい体型となります。
お腹を圧迫しない体位で、負担がかからないよう配慮する必要があります。
また、妊娠中は免疫力が低下しているため、感染症の危険性が高くなります。
性感染症を予防するためにも、必ずコンドームを使いましょう。
セックスをしている時に、お腹の張りを感じたり、気分が悪くなったりした時は、すぐに中断してください。
お腹の張りが治まらなかったり、出血したりした時は必ず受診しましょう。
切迫早産などの可能性がある場合には、セックスは厳禁です。
妊娠中のどの時期でもセックスはできますが、妊婦さんはお腹の赤ちゃんに意識が向いてしまうことが多くあります。
大切なのは、お互いを思いやる気持ちです。
体調がすぐれない時や、気がのらない時は、正直に断り、無理のない範囲でのセックスを心掛けましょう。
マタニティフォトを撮る

マタニティフォトを撮ることで、妊娠中の体型の変化や妊婦さんとパートナーの様子を記念に残すことができます。
最近では、スタジオなどでプロのカメラマンに撮影してもらう人も増えています。
妊娠は人生の中で数回しかない貴重な経験です。
妊娠期間にしかできない思い出作りとして挑戦してみてはいかがでしょうか。
子どもが大きくなった時に写真を見せると、お腹の中にいた時から大切にされていたと感じるかもしれませんね。
撮影を外部に依頼する際は、妊婦さんの体調にも配慮し、スケジュールを組んでください。
妊娠安定期に考えられるリスク
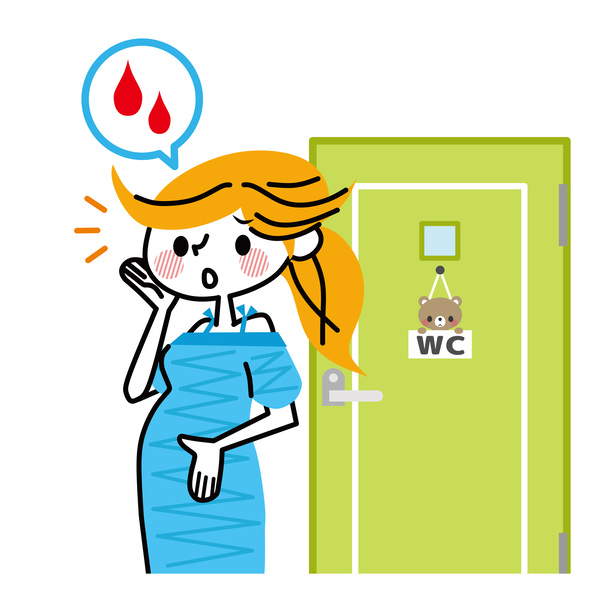
妊娠安定期には、下腹部痛や性器出血を伴うお腹の張りが起きることがあります。
妊娠12週を過ぎると流産のリスクは減りますが、それでも切迫流産や流産には引き続き注意が必要です。
妊娠安定期に入っていても、流産のリスクはゼロではありません。
流産の原因として、子宮発育不全などの母体の性器の異常や、高血圧などの全身疾患が考えられます。
流産リスクのある時期を過ぎても、周期的な下腹部痛やお腹の張り、性器出血がある場合は切迫早産や早産の可能性があります。
切迫早産の場合、痛みや出血以外にも、血液の混じったおりものが出たり、粘り気のあるおりものが増えたりします。
このような症状がある場合はすぐに受診してください。
切迫早産において、早期発見は大変重要です。
安静にして適切な治療を受けることで、少しでも長く赤ちゃんがお腹の中にとどまることができれば正期産の可能性も高まります。
妊娠安定期に旅行しても大丈夫?

最後の2人だけの時間を楽しむために、妊娠中に旅行を計画する人もいます。
妊娠中に旅行をするのであれば、妊娠安定期である妊娠5~7か月が良いでしょう。
ただし、万が一という事態にならないためには、いくつかの注意するポイントがあります。
妊娠中は血液量が増加し、血栓ができやすくなるため、移動手段には配慮が必要です。
車での移動は、こまめに休憩を取りましょう。
途中下車が難しい電車での移動は、体調が良好な時期を選んでください。
また、飛行機の場合、航空会社によっては、妊娠週数により医師の診断書が必要となることがあります。
必ず事前に確認してください。
旅行先として、長時間のフライトが必要となる海外旅行はおすすめしません。
ゆったりとしたスケジュールが組める国内の旅先を選びましょう。
テーマパークなどでの激しいアトラクションは避けてください。
旅行先で病院を受診する可能性もあるため、母子健康手帳と健康保険証は必ず持参しましょう。
また、市販薬を飲むことは避けた方がよいため、医師から処方された薬を忘れずに持っていきましょう。
万が一、旅先で体調が悪くなることがあれば、まずは主治医に相談してください。
もしもの時のために、旅先の近くにある産婦人科などを事前に調べておくとより安心です。
妊娠安定期に飛行機に乗っても大丈夫?

妊娠中に飛行機を利用する場合は、妊娠中期である妊娠16~27週が最も適しています。
妊娠初期には酸素濃度の低下によりつわりなどが悪化する場合もあり、妊娠後期には子宮を圧迫する原因にもなります。
そのため、里帰り出産などが目的で飛行機を利用する場合は、できる限り妊娠中期がよいでしょう。
妊娠中に飛行機を利用する場合には、いくつかの注意点があります。
まず、妊娠中のリスクとして挙げられるのが、エコノミークラス症候群です。
妊娠中は妊娠していない場合と比較して血栓ができやすいために、エコノミークラス症候群を引き起こしやすいと言われています。
飛行機に乗る際は、ゆったりとした服を着て、水分をこまめに摂取しましょう。
また、30分に1回は身体を動かしましょう。
次にリスクとして挙げられるのが、気圧の変化によるトラブルです。
気圧の変化は、胎児への影響はあまりないと考えられていますが、子宮が圧迫されたり、頭痛や頻尿が誘発されたりする原因となります。
通路側の席を予約する、マスクを着用するなどの対策をとりましょう。
妊娠中の飛行機の利用は、胎児より母体への影響が大きいため、妊娠の経過や体調を考慮し、医師と相談した上で、慎重に決めることが大切です。
まとめ

体調が安定し、比較的動きやすい妊娠安定期。出産に向けた準備とともに、マタニティフォトを撮るなどこの時期にしかできない体験をしておきたいですね。
しかし、リスクがないわけではありません。
母体と赤ちゃんの健康のためにも、体調に配慮し、無理をしないことが大切です。
注意すべきポイントをしっかりと把握し、充実したマタニティライフを送ってください。