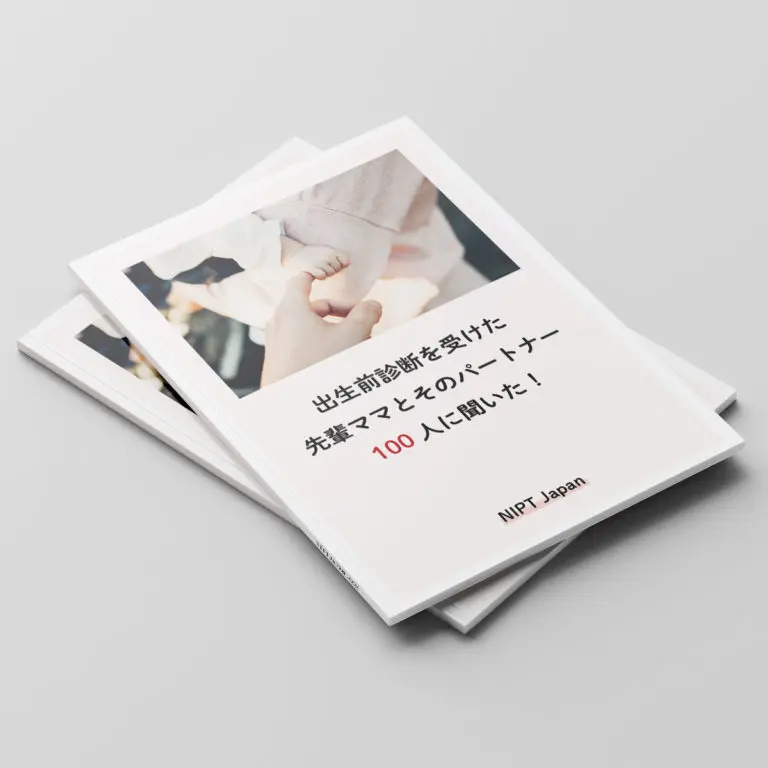胎児ドックとは胎児の発育に異常がないかを、精度の高い超音波機器を用いてより詳しく調べる検査のことです。
出生前診断の一種で、通常の妊婦健診ではわからないような先天性の病気や異常について、より詳細に検出することができます。
決まった名称はなく、「胎児精密超音波検査」などと呼ばれることもあります。
胎児ドックによって赤ちゃんの顔面構造、手足の数や形など外見でわかる形態異常だけでなく、心奇形や脳の異常といった臓器の状態、さらにダウン症などの染色体異常がある可能性まで調べることができます。
ここでは、胎児ドックでわかることやそのメリットとデメリットのほか、胎児ドックを受けるべきか悩んだときに考えてほしいことなどについてご紹介しています。
胎児ドックでわかること

通常の妊婦健診で行う超音波検査(エコー検査)では、赤ちゃんの発育状況のほか四肢などの見た目の異常、心臓などの各臓器の異常などを超音波画像から確認しています。
胎児ドックでは、3Dや4Dなどのより精度の高い超音波機器を使って、時間をかけて丁寧に診ます。
たとえば、胎児ドックではNTという胎児の首の後ろの厚みを表す値を測定しますが、NTが一定値以上あるとダウン症などの染色体異常がある可能性が高くなります。
通常の妊婦健診でNTの厚さを指摘されることもありますが、正確に測定するためには専門的な技術とそれなりの測定時間が必要になります。
【胎児ドックでわかること】
- 染色体異常(ダウン症、18トリソミー、13トリソミー)の可能性
- 脳の異常
- 無脳症
- 全前脳胞症
- 水頭症
- 先天性心疾患
- 顔貌の異常
- 鼻骨、顔面、耳などの位置
- 口唇裂
- 口蓋裂
- 手足の欠損
- 短肢異常
- 骨形成不全
- 消化器系の異常
- 臍帯ヘルニア
- 胃腸閉塞
- 腎臓の異常
- 泌尿器系の異常
- 腹壁欠損
- 脊髄髄膜瘤
通常の妊婦健診で行われる超音波検査では、胎児の成長、羊水の量、胎盤の位置などに焦点を当てていますが、胎児ドックではそれに加えて、先天性の病気や異常をより詳細に検出することが目的です。
特にダウン症やその他の染色体異常のリスク評価を行い、病気の早期発見に努めます。
メリット
【胎児ドックのメリット】
- 形態異常に強い
- 早期スクリーニングができる
- 流産のリスクがなく安全
- 費用が比較的安い
- 画像の解像度が高い
超音波画像から外見だけでなく内臓の様子も診ることができるため、骨の発達の様子や心臓弁の異常など、血液検査では分からないようなことを調べることができます。
胎児ドックは妊娠3ヶ月である妊娠11週頃から受けることができるため、早期に異常の発見や、その可能性を知ることができます。
これにより出産環境を整えたり、出生後の迅速な医療介入の計画を立てることが可能になります。
出生前診断の中には羊水検査や絨毛検査といった、妊婦さんのお腹に針を刺して検査をするものがあり、0.1-1%程度の流産リスクがありますが、胎児ドックはそういった侵襲的な検査はありませんので、母子ともに安全です。
そして出生前診断は自由診療のため高額になりがちで、羊水検査やNIPTなどは10-25万円程度かかりますが、胎児ドックは3-5万円程度と比較的安く受けることが出来ます。
通常の妊婦健診では断面の画像ですが、胎児ドックではより精度の高い機械を使っていることが多く、そのため胎児の成長と発達を3Dや4Dの立体として非常に高い解像度で観察できます。
デメリット
【胎児ドックのデメリット】
- すべての異常がわかるわけではない
- 染色体異常は可能性のみ
形態異常に強い胎児ドックですが、その範囲や胎児の姿勢によってはすべての見た目の異常がわかるわけではありません。
また超音波所見のない遺伝病や、形態異常でない視覚や聴覚などの異常も見つけることはできません。
心奇形や発育遅延などがあるとダウン症や18トリソミーなどの可能性を、NT肥厚があると特定の染色体異常を疑うことができますが、NT測定だけによるダウン症の検出率は70-80%であり、診断のためには追加検査を受ける必要があります。
胎児ドックを受けるタイミングと検査内容
多くのクリニックでは、「妊娠初期」「妊娠中期」「妊娠後期」に分けて段階的に胎児ドックを行い、胎児の成長に合わせて適切な検査を実施しています。
【初期】妊娠11-13週

この時期の胎児ドックは主に染色体異常のリスク評価に焦点を当てています。
【妊娠初期の胎児ドックでわかること】
- 染色体異常(ダウン症、18トリソミー、13トリソミー)の可能性
- 鼻骨の位置
- 心臓異常(心室中隔欠損症、心室肥大など)
- 頭と脳の異常
- 四肢の異常
- 顔面構造の異常
検査では胎児のNT(後頚部透明帯)の測定、鼻骨の有無、心臓や腹部の大きさ、頭と脳の構造、四肢の発達などを超音波で詳細に観察します。
NTの厚さは、ダウン症候群を含む染色体異常の指標の一つです。
また、この段階では心拍数や特定の血管の血流なども計測され、染色体異常の可能性を評価します。
染色体異常の可能性がある場合は、任意で追加の出生前診断を受けます。
【中期】妊娠18-22週

妊娠6ヶ月頃になると胎児の重要な器官はほぼできあがり、外性器も分かるようになります。
妊娠中期の胎児ドックは形態学的な詳細と生理的機能に重点を置いて実施されます。
【妊娠中期の胎児ドックでわかること】
- 脳の状態
- 心臓異常(心臓弁の異常など)
- 背骨の異常
- 顔面の異常(眼球、口唇、鼻のあな、顎、耳)
- 四肢の異常
- 染色体異常(ダウン症、18トリソミー、13トリソミー)の可能性
この時期には胎児の全身を精密に調べることができ、脳、心臓、背骨、顔、四肢などの細部に至るまで詳細な観察が可能です。
検査によって、脳の構造、心臓の室と弁の動作、胎児の背骨の整合性、四肢の成長状況などが評価されます。
また、この期間には腹部臓器の位置と構造もチェックされます。
【後期】妊娠28-32週

妊娠8ヶ月頃になると胎児は身長40cm、体重1.5kg程度まで成長し、筋肉や神経が発達してきています。
妊娠後期の胎児ドックは胎児の成長と発達の最終段階を確認し、出生に向けた準備を評価します。
【妊娠後期の胎児ドックでわかること】
- 大脳皮質の発達状態
- 心臓と主要な血管の機能
- 臓器の成熟度
- 染色体異常(ダウン症、18トリソミー、13トリソミー)の可能性
この段階では妊娠中期までの検査に加え、胎児の大脳皮質の発達状態、脳のしわの形成、心臓と主要な血管の機能、臓器の成熟度、そして胎児の全体的な健康状態が観察されます。
また、胎児が適切な体重を増加しているか、羊水の量が正常範囲内かなどもチェックされます。
この時期に行われる検査は、出産時に予期せぬ問題が起きるリスクを低減するのに役立ちます。
費用と保険適用の可能性

胎児ドックの費用相場は3万円から7万円程度です。
これは実施施設や検査項目によって大きく異なりますのであくまで目安とお考え下さい。
費用には検査料金のほかカウンセリング料や、かかりつけ医院でない場合は手数料がかかる場合があります。
胎児ドックを含む出生前診断は自由診療のため、公的医療保険は適用されず全額自己負担となります。
検査結果によっては追加の検査などでさらに高額になる可能性も考慮する必要があります。
胎児ドックを受けるべきか悩んだら
胎児ドックを受けるべきかどうかは、個々の状況や価値観、医学的リスク、経済的な考慮、さらには個人の心理的準備によって大きく異なります。
たとえば高齢出産や遺伝的リスクが高い場合、胎児に異常がある確率が一般より高くなるため、胎児ドックを受けるメリットは大きくなるでしょう。
胎児の健康状態に関する詳細な情報を得たいと考えている場合、胎児ドックは有益な選択肢です。
ただし赤ちゃんが染色体異常を持つ可能性があると結果が出た場合、心理的な準備ができていなけば予期せぬ結果に動揺してしまうことでしょう。
妊娠の継続を迷う場合は倫理的な問題や宗教的信念が関係してくることもあるでしょう。
胎児ドックはあくまで任意で選択できる検査です。
受けるかどうかの決定は、上記の要素を総合的に考慮した上で、パートナーや医療提供者との相談を通じて行うべきです。
全ての妊婦さんが胎児ドックを受ける必要はなく、個々の状況に応じて最善の決断をすることが大切です。
胎児ドックを含む出生前診断を受けるか悩む場合、遺伝医学の専門家に相談ができる「遺伝カウンセリング」をおすすめいたします。
NIPTとの違い
胎児ドックはダウン症、18トリソミー、13トリソミーといった染色体異常の可能性を調べることができますが、その検出率は他の出生前診断と比較するとけっして高いとは言えません。
一方で、胎児の心臓、脳、顔、四肢などといった形態異常については詳しく評価することができます。
NIPT(新型出生前診断)は母体血液中の胎児DNAを分析する検査のことで、非確定検査ながらダウン症、18トリソミー、13トリソミーについて高い精度で調べることができ、さらに施設によっては性染色体異常や微小欠失症なども検査が可能です。
まとめ

胎児ドックは形態異常のほか、特定の染色体異常の可能性について比較的安価で調べることができます。
ただし染色体異常についてはスクリーニング検査という位置づけで、可能性がある場合は羊水検査などで診断する必要がありますので、胎児ドックを受ける際は検査後の対応まで考慮したうえで検査に臨むことが大切です。
胎児に起こる主な染色体異常や先天性疾患の頻度についてはこちらをご参考にしてください。